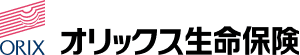高額療養費制度を活用したときの自己負担額は?
健康保険に加入している場合、医療費の自己負担分はかかった医療費の3割などとなります。
しかし、長期入院したときなどは自己負担額が高額になることもあり、「高額療養費制度」を活用することで負担を抑えることができます。
この制度は、同じ人が同じ月に、同じ医療機関でかかった一定割合の自己負担が自己負担限度額を超えたときに適用されます。
自己負担限度額は年齢や所得によって異なり、1か月あたりの金額が決まっています(下表参照)。
自己負担限度額
70歳未満
|
所得区分
|
自己負担限度額(月額)
|
多数回該当の場合*3
|
|---|---|---|
|
年収約1,160万円以上の所得者
健保:標準報酬月額83万円以上 国保:年間所得*1901万円超 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
|
140,100円
|
|
年収約770万〜約1,160万円の所得者
健保:標準報酬月額53〜79万円 国保:年間所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
|
93,000円
|
|
年収約370万〜約770万円の所得者
健保:標準報酬月額28〜50万円 国保:年間所得210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
|
44,400円
|
|
年収約370万円以下の所得者
健保:標準報酬月額26万円以下 国保:年間所得210万円以下 |
57,600円
|
44,400円
|
|
住民税非課税者
|
35,400円
|
24,600円
|
- 「年間所得」とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額です。
70歳以上
|
区分
|
自己負担限度額(月額)
|
多数回該当の場合*3
|
|
|---|---|---|---|
|
通院(個人ごと)
|
入院および通院
(世帯ごと) |
||
|
年収約1,160万円以上の所得者
健保:標準報酬月額83万円以上 国保、後期:課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
|
140,100円
|
|
|
年収約770万〜約1,160万円の所得者
健保:標準報酬月額53〜79万円 国保、後期:課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
|
93,000円
|
|
|
年収約370万〜約770万円の所得者
健保:標準報酬月額28〜50万円 国保、後期:課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
|
44,400円
|
|
|
年収156万〜約370万円の所得者(一般)
健保:標準報酬月額26万円以下 国保、後期:課税所得145万円未満 |
18,000円
(年間上限14.4万円) |
57,600円
|
44,400円
|
|
住民税非課税者(低所得世帯)
|
8,000円
|
24,600円
|
ー
|
|
うち所得が一定以下*2
|
15,000円
|
||
- 年金収入のみの場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの人。
- 同一世帯で1年間(直近12か月)に3か月以上、高額療養費が支給されていると、4か月目以降自己負担限度額が軽減されます。
例:70歳未満・年収約370万円~約770万円の方の場合
(暦月(月の初めから終わりまで)の医療費が100万円、自己負担3割の場合)
(暦月(月の初めから終わりまで)の医療費が100万円、自己負担3割の場合)


高額療養費でカバーされない費用は?
- 入院時の食事代などの一部負担
- 差額ベッド代
- 先進医療にかかる技術料
- 交通費、入院に際しての日用品代、入院証明書発行費用、快気祝いなど
高額療養費を受けるには?
病院窓口でいったん自己負担分(3割など)を支払い、後日請求(申請)する方法と、事前に交付を受けた「限度額適用認定証」を提示し、窓口での支払額を自己負担限度額までとする方法があります。