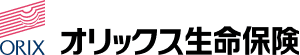生命保険(死亡保険)の選び方は?おすすめの種類や年代・世帯別のポイントを紹介
生命保険とは、被保険者に万一のことがあったときに、保険金が支払われる保険です。生命保険には、さまざまなタイプの商品があり、「自分に適したものをどう選べばいい?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
本記事では、生命保険の種類や必要性、年代・世帯別に保険を選ぶときのポイントなどを解説します。ご自身に適した保険を選択するための参考にしてください。
生命保険とは?
生命保険とは、その名のとおり「人の生命」に関する保険です。自分や家族が亡くなった場合の遺族の生活費や、長生きした場合の老後の生活費など、人生において起こり得る “生命に関する万一”に経済的に備えられるものです。
同じ保険でも、損害保険は自動車事故や火災などによって、自動車や家といった物品の経済的損失を被った場合に備えるもので、性質が異なります。
生命保険の仕組み
生命保険は、加入者がお互いに助け合う「相互扶助」の仕組みで成り立っています。保険に加入した人が少しずつ出し合った保険料が、“生命に関する万一”に遭ってしまった加入者に支払われる保険金や給付金の原資となります。
一人では出せない金額も、多くの人が出し合うことで、まかなうことが可能です。この相互扶助の仕組みは生命保険だけでなく、損害保険や公的年金、健康保険などの保険全般に取り入れられています。
また、生命保険は多くの場合、基本となる主契約とオプションである特約で構成されています。
たとえば、死亡に備える死亡保険であれば、基本の死亡保障に加えて、不慮の事故や所定の感染症による死亡や高度障害の場合に追加で保険金を受取れる「災害割増特約」や、がん・急性心筋梗塞・脳卒中などの所定の状態の場合に保険金を受取れる「特定(三大)疾病保障特約」を付けたりできます。
他にも多くの特約が商品ごとに用意されており、ご自身のライフステージや健康状態などを考慮して、必要な保障を追加して契約します。
生命保険と医療保険
生命保険は、万一亡くなった場合の遺族保障のための仕組みとしてできたものです。一方、時を経て、人々のニーズに応じて生まれたのががん保険をはじめとする医療保険です。
契約時に定めた保険金額を被保険者が亡くなったときに遺族が受取る死亡保険と異なり、医療保険は被保険者が入院や手術をしたときに給付金を受取ります。
死亡保険に医療保障の特約を付けたものや、医療保険に死亡保障がついているものなど、生命保険と医療保険を組み合わせたものもあります。
日本の生命保険加入者データ
18歳から79歳までの人を対象にした生命保険文化センターの調査結果によると、79.8%の人が生命保険または医療保険に加入しているようです。どんなときに備えて加入しているのか、保障内容ごとにみてみましょう。
保障内容ごとの加入率
| 保障内容 | 加入率 |
|---|---|
|
病気やケガの場合に入院給付金が支払われる保険
|
68.8%
|
|
がんの場合に給付金が支払われる保険や特約
|
39.1%
|
|
特定疾病(がん・心筋梗塞・脳卒中など)の場合に保険金が支払われる保険や特約
|
30.9%
|
|
老後保障として年金が支払われる保険
|
18.9%
|
- 公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」
なお、死亡に備えた経済的準備として生命保険と回答した人は全体の60.3%でした。多くの人が死亡や病気などに備えて保険に加入しています。
生命保険(死亡保険)は、何のために必要?
生命保険(死亡保険)は、主に「万一」の場合に遺族が安心して暮らしていけるよう、まとまった資金を確保するために活用されています。
「万一」に備えるには、生命保険(死亡保険)以外にも預貯金という方法があります。預貯金は、お金の出し入れがしやすい反面、まとまった金額が貯まるまで時間がかかるため、万一のときに十分な金額が準備できない可能性があります。
一方、生命保険(死亡保険)は、あらかじめ受取れる金額が決まっている(※)ため、保険期間内であればいつでもまとまったお金を受取ることができます。万一のときはいつ訪れるかわかりません。商品の特徴を比較し、自分にあった方法で備えることが大切です。
- 収入保障保険を除く
貯蓄との違い
「万一への備え」でも、生命保険と預貯金は特徴が異なり、「貯蓄は三角、保険は四角」とたとえられます。
-
貯蓄
備え始めたときには使えるお金はなく、「そのとき使える金額(貯蓄額)」は少しずつ増えていくため三角形になるのが特徴です。
-
保険
保険は、備え始めようと加入したときから、万一のときには契約時に定めた金額(保険金額)を受取ることができるため、四角形で表されます。ただし、預貯金のように自由にお金を引き出したりはできません。
貯蓄は、時期によっては備えられる金額が少なくなりますが、保険は、加入したその日に何かがあってもまとまったお金を受取れる場合があります。


生命保険に加入するメリット
生命保険は万一のリスクに備えられるだけでなく、相続税の納付資金の準備に活用できたり、保険料控除によって所得税や住民税の負担を軽くできたりといったメリットがあります。生命保険に加入した際のメリットをご紹介します。
生命保険に加入するメリット4つ
(1)死亡への備えができる
一家の大黒柱やパートナーが亡くなった場合の経済的損失に備えられます。葬儀代など死亡時にかかるお金だけでなく、遺族の生活費や子どもの教育費に保険金を充てることができます。
(2)貯蓄ができる
解約払戻金のある貯蓄型生命保険は、保障が不要になった際に解約をするとまとまった金額が受取れます。たとえば、子どもが小さいうちは死亡保障を目的とし、保障が不要になったタイミングで解約すれば、子どもの独立資金やご自身の老後資金として活用できます。
(3)相続対策にもなる
通常、相続財産は相続人全員による遺産分割協議を経なければ動かすことができません。しかし、生命保険なら保険金受取人を指定するため遺言がなくても遺したい人にスムーズにお金を渡せます。
また主な相続財産が自宅の場合、相続税の納税資金が不足するケースにおいては、保険金を納税資金に充てられます。相続人が保険金を受取る場合に限り、「500万円×法定相続人数」が非課税となる点も大きな特徴です(契約者と被保険者が同じ場合)。
(4)生命保険料控除を利用できる
税制上の制度である生命保険料控除を使うことによって、保険の契約者が支払う所得税や住民税を少なくすることが可能です。
たとえば、死亡保険に年間8万円を超える保険料を払っている場合、所得税を計算する上で所得から4万円を控除できます。
生命保険料控除は、次のように3つの項目ごとに上限が決められています。
|
生命保険料控除
|
介護医療保険料控除
|
個人年金保険料控除
|
|---|---|---|
|
最高4万円
|
最高4万円
|
最高4万円
|
死亡保険で受けられる控除に加えて、医療保険や介護保険に保険料を払った場合で最大4万円、個人年金保険に保険料を払った場合で最大4万円です。つまり、3つの項目を合わせて最大12万円の控除を受けることが可能です。
- 平成24年1月1日以後の新契約の場合です。以前の旧契約については控除額の計算方法が異なります。
- 上記は、2025年2月の税務取扱いに基づいたもので、将来的に変更となる可能性があります。具体的な事例については、所轄の税務署や税理士などの専門家にご相談ください。
生命保険の種類
生命保険は「死亡保険」「生存保険」「生死混合保険」の大きく3つの種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分に合った保険選びの参考にしてください。
生命保険(死亡保険)とは
生命保険(死亡保険)とは、保険期間中に被保険者が亡くなったときに保険金が支払われる保険です。死亡に備える生命保険(死亡保険)は、「定期保険」と「終身保険」の大きく2種類あり、それぞれ特徴が異なります。
主な生命保険(死亡保険)の概要
| 定期死亡保険 |
一定期間保障が続く死亡保険 |
|---|---|
| 終身死亡保険 |
一生涯保障が続く死亡保険 |
定期保険
定期保険とは、保障が一定期間の保険です。定期死亡保険では、保険期間満了までの間に被保険者が亡くなったときに保険金が支払われます。
定期死亡保険は掛け捨て型であることがほとんどのため、保険料負担を抑えつつ大きな保障を確保できます。10年で満了となる短期のものや、35年(あるいは90歳)で満了する長期のものまで、さまざまなタイプがあります。
終身保険
終身保険とは、保障が一生涯続く保険です。定期保険と異なり、途中で保障が切れることなく、一生涯保障が続きます。そのため定期保険と比較すると、保険料は割高な傾向にあります。
また、生命保険には、「死亡保険」の他に「生存保険」と「生死混合保険」があり、特徴と代表例は次のとおりです。
生存保険とは
生存保険は、被保険者が保険期間の満了時に生きている場合に限り、保険金や満期金、年金などが支払われる保険です。保険期間中に亡くなった場合は、一定の死亡保険金が支払われます。
死亡保険のように、遺族保障として大きなお金をもらえるものではありません。受取ったお金を、被保険者本人が学資や老後の生活費などに使いたい場合に加入する保険です。
代表的な生存保険
-
学資保険
学資保険は、子どもの教育資金を準備するための保険です。進学時、満期時などに学資金が支払われます。契約者が亡くなった場合は、一般的に以後の保険料支払いが免除されます。
-
個人年金保険
個人年金保険は、老後の生活資金を準備するための保険です。生死にかかわらず受取開始年齢から5年や10年などの一定期間年金を受取れる確定年金や、被保険者が生きている間は契約時に定めた一定期間年金を受取れる有期年金、生きている間ずっと受取れる終身年金などがあります。
生死混合保険とは
生死混合保険は、生存保険と死亡保険をミックスした保険です。保険期間中に亡くなった場合に、保険金受取人に死亡保険金が支払われます。保険期間終了時に生きていれば、生存保険金(満期金)が支払われます。
代表的な生死混合保険
-
養老保険
養老保険は、満期を迎えると満期保険金が支払われる保険です。満期前に亡くなった場合は、満期保険金と同額の死亡保険金が支払われます。
その他の種類
生命保険会社が扱う保険には上述の種類以外に、さまざまなリスクに備えられる以下のような保険があります。
-
医療保険
医療保険は、病気やケガによる入院や手術をしたときに給付金が支払われる保険です。特約を付けることによって、三大疾病やがんの保障を手厚くすることができます。
-
がん保険
がん保険は、がんと診断された場合に一時金が支払われたり、がんの治療のために通院、入院、手術をしたときに給付金が支払われたりする保険です。
-
介護保険
介護保険は、所定の要支援・要介護状態になった場合に、給付金を受取れる保険です。
定期(掛け捨て)保険と終身保険はどちらがおすすめ?
死亡保険には、大きく分けて「定期(掛け捨て)保険」と「終身保険」の2種類があります。
それぞれメリット・デメリットがあるため、死亡保険に加入する際は両方の特徴を理解することが大切です。
定期(掛け捨て)の一般的なメリット・デメリット
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
定期(掛け捨て)保険は、少ない保険料で大きな保障が得られるため、保障を厚くしたい期間が決まっている方などに向いています。一方、更新時に保険料が上がる点がデメリットですが、更新時に保障額を調整することで家計への負担を抑えられるでしょう。
定期(掛け捨て)保険は、以下のようなケースに向いています。
-
子どもが独り立ちするまでの保障を手厚くしたい
保険料負担を抑えられるため、養育費や家族のイベント費用を圧迫せずに手厚い保障を受けることが可能です。
-
自営業者などが専業主婦(主夫)である配偶者の生活費に備えたい
子がいない自営業者が亡くなった場合、ご家族へ公的遺族年金が支給されません。そのため、配偶者が専業主婦(主夫)の世帯は、配偶者が老齢年金を受給できる年齢になるまでの備えとして活用できます。
終身保険のメリット・デメリット
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
終身保険は、一生涯の保障を得ながら資産形成も行えるのが大きなメリットです。一方、掛け捨てタイプと比べると保険料は割高になる傾向があります。解約払戻金があるとしても、払込保険料の総額を下回る可能性があるため、保険料が生活や家計を圧迫するリスクについても考慮する必要があるでしょう。
終身保険は、以下のようなケースに向いています。
-
一生涯の保障が必要
保険期間が一生涯であれば、遺族に、確実にお金をのこすことが可能です。人が亡くなった際、葬儀費用、遺品整理費用、家族の生活費、相続費用などが発生する場合があります。一生涯の保障があれば、遺族は急な出費があった際も経済的な負担を軽減し不安なく過ごせるでしょう。
-
場合によっては生前にも活用したい
保障が不要になった場合、終身保険は一定期間経過後にまとまった解約払戻金を得ることができます。解約払戻金は子どもの教育費やセカンドライフの資金など、さまざまな資金として活用することが可能です。
ライフステージ別の生命保険(死亡保険)を選ぶ時のポイント
結婚や出産など、家族構成や将来の展望などのライフステージによって必要な保障も変わってきます。以下のライフステージ別の生命保険の選び方を参考に、ご自身に適した生命保険を選びましょう。
単身の場合
年齢にかかわらず万一のことが起こる可能性はあります。万一の場合は、葬儀代や自身の身辺整理にお金がかかります。また、将来的に結婚したり子どもができたりすると、生命保険の重要度が増す場合もあります。今後のために、金銭的に無理のない範囲で加入しておくとよいでしょう。
40代~50代単身の場合、貯蓄が十分であれば死亡保険の必要性は低いことが多いでしょう。ただし、ご両親が既に退職しており、ご自身が世帯主になっている、もしくは経済的援助を行っている状況であれば万一の場合に備えておくと安心です。
また、ご自身の老後資金を形成するために、終身保険に代表される貯蓄型生命保険に加入する選択肢もあります。
生命保険は健康状態や病歴などによって加入できなくなるケースがあるため、健康なうちから生命保険に加入しておくと安心です。
既婚(子なし)の場合
自分自身の医療保険・がん保険に加え、遺族(パートナー)のための死亡保険も考える必要があります。
片働きの場合
パートナーが専業主婦(夫)であれば、生活できるだけの貯蓄が必要です。ただし、パートナーが20代や30代と若い場合は、その後の生活費をすべてまかなう額を死亡保障で用意するのは簡単ではありません。万一のときは、専業主婦(夫)の方も働きに出ることも検討しましょう。
共働きの場合
共働きでパートナーの収入がある程度確保できている場合は、死亡保障額もそれほど多くは必要ないといえます。しかし、夫婦のどちらかがパート勤務などで収入が少ない場合、死亡保険でカバーしておくと安心です。
既婚(子あり)の場合
子どもがいる場合は、万一のときにパートナーや子どもの生活費を確保するためにも、生命保険の重要性が増します。
片働きの場合
パートナーの生活を守るための費用と、子どもが成人するまでの学費や生活費が必要です。子どもが小さいうちはパートナーが仕事を見つけにくいかもしれません。また、どちらかに病気やケガなど万一のことが起こると、生活が困難になる可能性があるため、リスクに備えて必要額をシミュレーションしましょう。
共働きの場合
共働きの場合は、家計における自分の収入の割合を考慮してシミュレーションし、必要な額を決めるといいでしょう。ただし、どちらかの死亡によってひとり親となった場合、それまでと同じように収入が得られるとは限りません。特に子どもが小さい場合は、育児の負担も考慮して必要額を検討しましょう。
なお、死亡による生活費の不足額を補いたいときは、子どもの成長に合わせて保障額を調整しやすい定期保険や収入保障保険が向いています。
既婚(子独立後)の場合
共働き、片働きに関わらず、定年までは生命保険の重要性が高いですが、健康リスクも高くなるので医療保険も検討する必要があります。若年層と比べて保険料が高くなる傾向にあるため、子どもが独立した、夫婦の働き方が変わった、定年退職したなどライフステージの変化に応じて、必要保障額の見直しをするとよいでしょう。
また、貯蓄型生命保険がある場合は、いつ保障が不要になりそうか、あるいは解約しないなど将来的な活用方法についても家族で話し合っておくと有効活用につながります。
万一のとき、のこされた家族にどれくらいお金が必要?
保険商品を選ぶ際のもうひとつのポイントは、保険金額です。
一家の大黒柱に万一のことがあったら、収入と支出のバランスが一気に崩れてしまいます。生命保険文化センターの調査結果によると、生命保険に加入している方のうち、約34.2%*が現在の保障内容では不安に思っています。
万一の際に必要な保障額は、その家庭の現在の収入や年金の受取予定額、家族の生活水準や子どもの進学先などによって異なります。
- [出典]公益財団法人生命保険文化センター 「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」
必要保障額の決め方
万一のときにいくら必要になるかを試算した金額を「必要保障額」といいます。
保険選びはこの必要保障額をもとに考えていきます。算出方法は以下のようになります。


※ 必要保障額シミュレーションで算出できます
想定している生活プランをもとに、将来の収支のバランスを「見える化」して、のこされたご家族にいくらお金が必要になるか、きちんと計算するところから始めることが大切です。
自分で調べてみたけれど本当にこれでいいの?と不安に感じられる方は、保険会社の担当者やファイナンシャル・プランナーへご相談ください。
希望を伝えることで、必要な保障額についてシミュレーションをしてもらえます。
ライフステージや目的に応じた生命保険を選択しよう
さまざまな種類のある生命保険ですが、ご自身の年齢や家族構成によって適切な生命保険は異なります。また、生命保険への加入後は、ご自身のライフステージに合った保障内容にするため、定期的な見直しも重要になります。
まずは目的や現状考えられるリスクを踏まえ、自分に合った保障を検討してみてはいかがでしょうか。
パンフレットを見て検討
資料請求保険選びでお困りですか?
- 葬儀費用を準備する保険の選び方
- 生命保険(死亡保険)の選び方は?おすすめの種類や年代・世帯別のポイントを紹介
- 老後から考える死亡保険の選び方(85歳まで入れる死亡保険)
- 死亡保険の「掛け捨て型」と「貯蓄型」どちらを選ぶ?
- 生命保険(死亡保険)と医療保険にかかる税金をわかりやすく解説!税の種類や非課税枠について
- 死亡保険金はいくら必要?
- 死亡保険の必要性が高い人ってどんな人?
- 死亡保険(生命保険)の「定期保険」と「終身保険」、ライフステージ別契約例のご紹介
- ご存じですか?先進医療のこと
- オリックス生命の3種類の医療保険(入院保険)。保障内容の違いは?
- 三大疾病、七大生活習慣病とは?
- 医療保険なんでも相談室
- 手術給付金から考える医療保険
- 妊娠・出産にかかる費用、公的支援制度と備え方
- 医療保険の払込期間とは?短期払(60歳払・65歳払など)と終身払の違いと選び方
- 医療保険の保険料や保障額の相場は?年齢別・性別・世帯年収別に解説!
- がん保険の選び方
- がん保険の「終身タイプ」と「定期タイプ」の違いは?