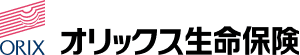生命保険(死亡保険)と医療保険にかかる税金をわかりやすく解説!税の種類や非課税枠について
生命保険にかかる税金は、契約形態や保険金の受取り方によって種類が異なるため、複雑と感じる人も少なくありません。しかし、税金について知っておくことで少しでもその負担を軽減し、生命保険をより有効に活用することができます。
ここでは、保険料を支払った際の生命保険料控除や、保険金を受取った際の税金の種類の違いについて解説します。あわせて、生命保険の死亡保険金や医療保険の給付金が非課税となるケースも紹介します。
1.保険料を支払った場合の所得控除
まずは、生命保険や医療保険の保険料を支払った際に受けられる「所得控除」について確認しましょう。
生命保険(死亡保険)と医療保険の保険料は所得控除の対象になる
生命保険に加入すると、毎年支払う保険料に応じて生命保険料控除が利用でき、所得税や住民税の負担が軽くなります。
保険料を支払うと、毎年10月頃に保険会社から生命保険料控除証明書が郵送されます。この書類を年末調整時に勤務先に提出すると、後日、給与から引かれていた所得税の一部の払戻しを受けられます。
年末調整に書類の提出が間に合わなかった会社員や、自営業者やフリーランスなどをしている人は、翌年に確定申告をして生命保険料控除証明書を提出することで、同様に所得税の払戻しや軽減を受けられます。
生命保険料控除を利用すると、翌年の住民税負担を減らす効果もあります。
所得税の生命保険料控除額は、最大で12万円
生命保険料を支払うことで生命保険料控除を受けられますが、その所得控除額は最大で年間12万円です。
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険の場合、加入している保険の種類によって、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3つの種類に分けられます。
3つの枠それぞれで8万円超の保険料を支払った場合には、各4万円の所得控除を受けられるため、合計で年間最大12万円の所得控除を受けられます。
2011年(平成23年)12月31日以前の契約も生命保険料控除の対象ですが、この場合は旧契約扱いとなり控除額が異なります。
旧契約は、生命保険(死亡保険)、医療保険、介護保険などを含む一般生命保険料控除と、個人年金保険料控除の2種類に分けられます。2つの枠でそれぞれ10万円超の保険料を支払った場合に、各5万円の所得控除を受けられるため、合計で年間最大10万円の所得控除を受けられます。
- 令和8年のみの実施となりますが、23歳未満の扶養親族を有する人について一般生命保険料控除が拡大されています。
2.生命保険(死亡保険)の保険金を受取った場合の税金
生命保険金(死亡保険金)が支払われた場合、保険料を負担した契約者、保障の対象となる被保険者、保険金の受取人が、それぞれ誰であるかによって、税金の種類が異なります。
生命保険金(死亡保険金)の課税関係
| 契約者(保険料の負担者) | 被保険者(保障の対象となる人) | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
|
A
|
A
|
B
|
相続税
|
|
A
|
B
|
A
|
所得税
|
|
A
|
B
|
C
|
贈与税
|
相続税:契約者=被保険者の場合
例えば、夫が自分の万一に備えて生命保険(死亡保険)に加入して保険料も自分で支払っていた場合、夫が死亡して妻や子どもが生命保険金(死亡保険金)を受取ると、相続税の対象となります。このように相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同一の場合です。
生命保険(死亡保険)は遺族の生活を守るという趣旨から、相続人が受取った生命保険金(死亡保険金)には、法定相続人の数に応じた生命保険の非課税枠が適用されます。そのため、生命保険金(死亡保険金)でのこすと現金などで相続するよりも相続税の負担を軽くすることができます。
この制度については、「3.生命保険金(死亡保険金)にかかる相続税の非課税枠と基礎控除額」で詳しく説明します。
ただし、収入保障保険のように、生命保険金(死亡保険金)が年金形式で支払われる保険の場合には、相続した年に受取った生命保険金(死亡保険金)については相続税の課税対象となりますが、2年目以降に受取る額は所得税の対象となります。
所得税:契約者=保険金受取人の場合
例えば、妻が亡くなったときに、それまで妻の保険料を支払っていた夫が、生命保険金(死亡保険金)を受取ると所得税の対象となります。このように所得税の対象となるのは、契約者と保険金受取人が同一の場合です。
この場合、生命保険金(死亡保険金)を一時金で受取ると一時所得扱い、年金形式で受取ると公的年金など以外の雑所得扱いになり、それぞれ税金の計算方法が異なります。
贈与税:契約者≠被保険者≠保険金受取人の場合
例えば、妻が亡くなったときに、それまで夫が保険料を支払っていた生命保険(死亡保険)から、子どもが保険金を受取ったという場合には、贈与税の対象となります。
このように、保険料を負担していた契約者と、保障の対象だった被保険者、生命保険金(死亡保険金)の受取人がすべて異なる場合、贈与税の対象となります。
3.生命保険金(死亡保険金)にかかる相続税の非課税枠と基礎控除額
既述のとおり、生命保険(死亡保険)の契約者=被保険者の場合、保険金に相続税がかかります。ここでは、相続税の非課税枠と基礎控除額の概要を紹介します。
生命保険金(死亡保険金)には相続税の非課税枠がある
相続人が受取った生命保険金(死亡保険金)は、生命保険金(死亡保険金)の非課税枠が適用されるため、現金で同額を相続するのに比べると相続税負担を軽くする効果があります。
相続人が受取った生命保険金(死亡保険金)の合計額が、以下の計算式の非課税枠をこえるときには、超過分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税枠
基礎控除額によって相続税がかかる人、かからない人がいる
相続が発生しても必ず相続税がかかるわけではありません。国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によると、令和5年分提出申告書のうち相続税の課税対象となったのは9.9%です。
その理由は、相続税には基礎控除額があり、相続財産がその範囲内であれば相続税を支払う必要がないからです。相続税の基礎控除額は、以下のとおりです。
相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、配偶者と子ども3人をのこして死亡したAさんの財産が7,000万円あったとします。このうち、自宅と預貯金などの合計が4,000万円、死亡したAさんが保険料を負担していた生命保険金(死亡保険金)が3,000万円だったとします。この場合、生命保険金(死亡保険金)については、「500万円×4名=2,000万円」が非課税となるため、残りの1,000万円が相続税の課税対象となります。
自宅と預貯金などの合計4,000万円と生命保険金(死亡保険金)1,000万円の合計5,000万円が課税相続財産となります。配偶者と子ども3人をのこして亡くなった場合には、「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」の相続税の基礎控除額があるため、このケースでは課税相続財産が相続税の基礎控除額に収まり、相続税はかかりません。
相続財産の一部を生命保険という形でのこすことで、相続税負担を軽減できたケースです。
4.満期保険金を受取った場合の税金は所得税・源泉徴収・贈与税に注意
満期保険金を受取った場合の税金は、所得税(住民税を含む)、源泉所得税、贈与税があります。それぞれどのようなケースで発生するのかご紹介します。
所得税(一時所得/雑所得/源泉所得税)がかかるケース
| 契約者(保険料の負担者) | 被保険者(保障の対象となる人) | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
|
A
|
B(Aでも可)
|
A
|
所得税
(一時所得/雑所得/源泉所得税) |
所得税(一時所得)が課税されるケース
契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同じ場合は、一時所得として所得税が課税されます。
一時所得の課税金額は、以下の計算式で算出します。
一時所得の課税金額=(満期保険金-払込んだ保険料の総額-特別控除50万円)×1/2
- ほかの一時所得がある場合は特別控除の前に合算します。
このように、一時所得には50万円の特別控除があるため、満期保険金から払込んだ保険料を差引いた金額が50万円以下の場合は税金がかかりません。
所得税(雑所得)が課税されるケース
契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同じでも、年金として受取る場合は、雑所得として所得税が課税されます。
雑所得の課税金額は、以下の計算式で算出します。
雑所得の課税金額=その年の年金額―必要経費*
- 必要経費=年金年額×(払込保険料の合計額/年金の総支給見込額)
所得税(源泉所得税)が課税されるケース
契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同じでも、契約していた保険が金融類似商品*の場合は、源泉分離課税として源泉所得税が課税されます。
- 所定の要件を満たす一部の保険商品。5年満期の一時払養老保険など
贈与税が課税されるケース
| 契約者(保険料の負担者) | 被保険者(保障の対象となる人) | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
|
A
|
B
|
C
|
贈与税
|
|
A
|
A
|
C
|
|
|
A
|
B
|
B
|
- 例:A=本人 B=配偶者 C=子どもの場合
契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が異なる場合は、受取人に贈与税が課税されます。
贈与税の課税対象は、以下の計算式で算出します。
贈与税の課税対象=満期保険金―基礎控除110万円
このように、贈与税には110万円の基礎控除があるため、その年のすべての贈与の合計が110万円以下の場合税金はかかりません。
5.生命保険(死亡保険)と医療保険で非課税になる保険金・給付金
生命保険や医療保険の保険金や給付金には、受取っても非課税となり税金がかからないものがあります。代表的なものは以下のとおりです。
- 死亡保険金のうち、相続税の非課税枠に該当する部分
- 医療保険の入院給付金、手術給付金、通院給付金、がん診断給付金など
- 死亡保険の高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金など
- 被保険者が給付金を請求する前に死亡した場合、未請求の給付金は相続財産となり相続税の課税対象となります。
6.生命保険(死亡保険)にかかる税負担を抑えるためのポイント
なるべく税の負担を抑えることができるよう、意識したいポイントをご紹介します。
契約者と保険金受取人の関係に注意
保険金を受取る際の税負担を抑えるためには、契約者(保険料負担者)を被保険者(保障の対象となる人)と同一にし、保険金受取人は相続人とする形が理想的です。この場合、保険金は相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠も活用することができます。
上記のような形が難しい場合は、契約者と保険金受取人を同一として、所得税の課税対象になるようにしましょう。相続税として非課税枠を活用する場合には劣るものの、贈与税の課税対象になるよりは、一般的に税の負担を抑えることができます。
生命保険料控除をしっかり活用する
保険料を支払った際には「生命保険料控除」を忘れずに活用しましょう。支払った保険料に応じて所得税や住民税の負担が軽減され、トータルの家計への税負担を抑えることができます。
会社員であれば、年末調整の際に申告書を記入し、生命保険料控除証明書を提出します。医療保険や個人年金保険も控除の対象です。また、配偶者の生命保険であっても、本人が保険料を負担している場合は生命保険料控除を受けられます。
生命保険(死亡保険)と医療保険について、かかる税金やその種類を知っておこう
このように、生命保険や医療保険の保険金・給付金を受取る際には税金がかかることが多く、その種類は契約形態や受取り方によっても異なります。
そのようなときに、非課税となるケースや控除制度をきちんと理解しておくことで、家計への税負担の軽減につながります。
保険金や給付金を実際に受取るときに備え、税金の仕組みを事前に把握したうえで保険に加入することが大切です。
- 記載の内容は2025年8月現在の税制によります。今後、税制の変更にともない、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱に関してご不明点がある場合は、所轄の税務署や税理士等、専門家にご相談ください。
パンフレットを見て検討
資料請求保険選びでお困りですか?
- 葬儀費用を準備する保険の選び方
- 生命保険(死亡保険)の選び方は?おすすめの種類や年代・世帯別のポイントを紹介
- 老後から考える死亡保険の選び方(85歳まで入れる死亡保険)
- 死亡保険の「掛け捨て型」と「貯蓄型」どちらを選ぶ?
- 生命保険(死亡保険)と医療保険にかかる税金をわかりやすく解説!税の種類や非課税枠について
- 死亡保険金はいくら必要?
- 死亡保険の必要性が高い人ってどんな人?
- 死亡保険(生命保険)の「定期保険」と「終身保険」、ライフステージ別契約例のご紹介
- ご存じですか?先進医療のこと
- オリックス生命の3種類の医療保険(入院保険)。保障内容の違いは?
- 三大疾病、七大生活習慣病とは?
- 医療保険なんでも相談室
- 手術給付金から考える医療保険
- 妊娠・出産にかかる費用、公的支援制度と備え方
- 医療保険の払込期間とは?短期払(60歳払・65歳払など)と終身払の違いと選び方
- 医療保険の保険料や保障額の相場は?年齢別・性別・世帯年収別に解説!
- がん保険の選び方
- がん保険の「終身タイプ」と「定期タイプ」の違いは?