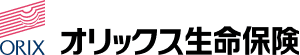手術給付金から考える医療保険
手術費用を保障する手術給付金。医療保険を選ぶ際には、手術給付金のどんなポイントに注目して選べば良いのでしょうか。手術給付金の2つのタイプの違いについて、手術の費用負担を軽くする公的制度とあわせてお伝えします。
手術給付金とは?
手術給付金とは、医療保険に加入している方が所定の手術を受けたときに受取れる給付金のことです。入院中の手術はもちろん、入院のない外来手術でも手術給付金を受取れます。
多くの医療保険では、入院給付金とともに手術給付金が主契約に組み込まれていますが、手術給付金がないものや、選択式の特約となっているものもあります。また、医療保険によって給付金額や保障の対象となる手術が異なっています。
手術給付金はどれぐらい保障してくれる?
手術給付金として受取れる金額には、大きく2つのタイプがあります。
(1)金額が一律で決まっているタイプ
対象となる手術であれば、どの手術に対しても一律の金額を受取れます。「手術を受けたらいくら」と、金額がわかりやすいところが大きな特徴でしょう。
例えば、約款で、手術給付金の金額が「入院給付金日額×20倍」と定められている場合、入院給付金日額が5,000円の契約なら手術給付金は10万円、入院給付金日額が1万円の契約なら手術給付金は20万円が、対象となる手術を受けた場合に受取れます。
(2)手術の種類によって金額が異なるタイプ
手術の種類によって、入院給付金日額の10倍、20倍、40倍というように、支払倍率を変えています。重大な手術には倍率が高く、比較的軽度な手術には倍率を低くするというように差を設けて、実際の負担額に対応しやすくしています。
手術給付金の支給条件にも注意しましょう。例えば、入院しないで手術を受ける日帰り手術の場合、支払いの対象外とする保険もあれば、入院による手術と同額支払う保険、日帰り手術の支給倍率を低めに設定している保険もあります。
手術給付金が支払われない手術もある?
手術給付金の注意点としては、治療目的でない手術は、手術給付金の対象外となることです。例えば、このような手術を受けても、手術給付金を受取れません。
- 美容整形などの手術
- レーシック手術
- 検査目的の手術
このほか、保険に加入する前からの病気を治すための手術や、加入前から予定した手術などは手術給付金の給付対象外になる場合があります。
手術費用の負担を軽くする公的な制度は?
医療保険はそもそも、公的医療保険の保障では足りない部分を補うために加入します。手術費用の負担を軽くできる公的な制度を知っておきましょう。
(1)高額療養費制度
高額療養費制度は、1か月の医療費負担に上限を設ける制度です。対象となる医療費は、公的医療保険の対象範囲に限られるため、入院中の差額ベッド代や食費、先進医療にかかる技術料などは高額療養費の対象外となります。
1か月当たりの上限額は、年齢や所得によって異なります。69歳以下の場合、上限額はこのようになります。
69歳以下の方の上限額
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
|---|---|
| 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 |
- 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
例えば、1か月の医療費総額が100万円だった場合、健康保険を使うと3割負担になるため、本来であれば1か月で30万円を負担することになりますが、高額療養費制度を使うと、さらに負担を軽減できます。
年収が約370万~770万円の場合、1か月の自己負担限度額の計算式はこのようになります。
「80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%」。
計算式に先ほどの医療費100万円を入れて、計算してみましょう。
「80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%」=87,430円
この場合、1か月の医療費負担は87,430円になります。
注意点としては、高額療養費を計算する際の1か月は「1日~月末まで」だということです。月をまたいで入院した場合には、それぞれの月ごとに計算します。
高額療養費が後払いの点にも注意が必要です。医療費を全額、医療機関で支払ってから、高額療養費の申請をすると、後日、自己負担限度額を超えた部分が、口座に振込まれるという仕組みです。
医療機関など窓口での負担を抑えたい場合には、健康保険組合などの窓口で「限度額適用認定証」を事前に入手しておきましょう。これを医療機関の窓口に提示すると、立替払いの必要がなくなり、医療費の支払いが限度額までに抑えられます。
(2)高額医療費貸付制度
医療費を支払うための資金を無利子で一時的に借りられる制度です。限度額適用認定証を用意していなかった場合、医療費を一度窓口で全額支払う必要がありますが、この制度を使うと、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で借りることができます。
(3)医療費控除
1年間(1月1日~12月31日)に負担した医療費が10万円または総所得金額の5%のいずれか低い金額を超えた場合に、確定申告をすることで、以下の計算式の金額を所得から差し引けます。その結果、納めた税金の一部が払戻しされます。
計算式
「支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円*」
- その年の総所得金額などが200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額の5%の金額
なお、医療費控除の金額は、所得から差し引ける金額です。医療費控除によって払戻しされる金額は、この金額に所得税の税率をかけた金額になるため、もっと少なくなります。
手術給付金の有無や保障内容を確認して医療保険を選ぼう
手術給付金はどれも同じではなく、それぞれの保険商品によって違いがあります。手術給付金は「金額が一律で決まっているタイプ」か「手術の種類によって金額が異なるタイプ」か、日帰り手術も対象となるのか、対象外となる手術にはどんなものがあるかを確認しておきましょう。高額療養費制度や医療費控除など、医療費の自己負担を軽減する制度がありますが、こうした公的保障の対象外となる費用もあります。これから医療保険への加入を検討している人は、手術給付金の有無やその内容について確認して、ご自身に合った医療保険を選びましょう。
パンフレットを見て検討
資料請求保険選びでお困りですか?
- 葬儀費用を準備する保険の選び方
- 生命保険(死亡保険)の選び方は?おすすめの種類や年代・世帯別のポイントを紹介
- 老後から考える死亡保険の選び方(85歳まで入れる死亡保険)
- 死亡保険の「掛け捨て型」と「貯蓄型」どちらを選ぶ?
- 生命保険(死亡保険)と医療保険にかかる税金をわかりやすく解説!税の種類や非課税枠について
- 死亡保険金はいくら必要?
- 死亡保険の必要性が高い人ってどんな人?
- 死亡保険(生命保険)の「定期保険」と「終身保険」、ライフステージ別契約例のご紹介
- ご存じですか?先進医療のこと
- オリックス生命の3種類の医療保険(入院保険)。保障内容の違いは?
- 三大疾病、七大生活習慣病とは?
- 医療保険なんでも相談室
- 手術給付金から考える医療保険
- 妊娠・出産にかかる費用、公的支援制度と備え方
- 医療保険の払込期間とは?短期払(60歳払・65歳払など)と終身払の違いと選び方
- 医療保険の保険料や保障額の相場は?年齢別・性別・世帯年収別に解説!
- がん保険の選び方
- がん保険の「終身タイプ」と「定期タイプ」の違いは?